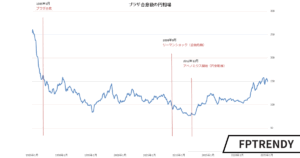中国にも「働き方改革」の兆し──“アフターワーク”が生活の主役に?
長時間労働の国・中国で始まった変化
「アフターワークこそが、本当の生活の始まりです」──。
2025年、美的集団(Midea)が公式WeChatに掲載したこのキャッチフレーズは、これまでの中国社会にはなかった新しい価値観を象徴しています。深夜までの労働が当然とされてきた中国で、午後6時20分に退社を求める企業の登場は、まさに“働き方”に変化が訪れている証しです。
他にも、DJI(ドローン最大手)は「午後9時にはオフィスを無人にする」方針を導入し、ハイアールは週5日勤務制度を導入するなど、長年続いてきた“996文化”(朝9時〜夜9時、週6日勤務)からの脱却を図る動きが見られます。
EU規制と政府方針が背中を押す
こうした動きは、単なる企業のイメージ改革にとどまりません。背景には、EUが2023年に導入した「強制労働製品の域内販売禁止」規制への対応があります。過度な残業も“強制労働”と見なされるため、中国企業は国際的なサプライチェーンに対応する必要に迫られているのです。
加えて、2025年3月に中国国務院が打ち出した「消費促進計画」では、労働者の休息・有給休暇取得を推奨する内容が盛り込まれました。消費主導の経済転換を進める中で、生活の質を高めることが必要不可欠だと判断されたのです。
とはいえ、まだ全体に広がっているとは言えません。多くのハイテク・金融業界では「007」(0時から0時、週7日)と揶揄されるほどの過酷な労働が続いているのも事実です。
🛌 「躺平」──出世競争から“降りる”選択
近年、中国の若者の間で「躺平(タンピン=横になる)」という言葉が共感を集めています。これは、過度な競争や長時間労働に抗い、出世や富の追求から距離を置くライフスタイルや考え方を指します。
「どうせ頑張っても報われないなら、最低限の生活でいい」という“諦め”ではなく、「自分の人生を自分で選ぶ」というポジティブな意思表示として広がっています。
この背景には、住宅価格の高騰、就職難、成果主義社会への疲労などがあり、特にZ世代の間で「ゆるく生きる」価値観が浸透しつつあります。
一方の日本──“働き方”をめぐる40年の試行錯誤
バブルと「24時間戦えますか」の時代
今から40年前、日本もまた“働きすぎ”の国でした。
1980年代後半、バブル経済に沸いた日本では、金融・建設・不動産を中心に長時間労働が当たり前でした。「24時間戦えますか」という企業CMが話題になり、“モーレツ社員”が美徳とされた時代です。男女問わず労働時間が延び、「過労死」という言葉が登場したのもこの頃です。
しかし、1987年の労働基準法改正で週40時間労働制が導入(段階的に施行)され、働き方の見直しが始まりました。
崩壊後の「失われた10年」と非正規時代
1990年代に入るとバブルが崩壊し、日本は長い不況に突入します。企業は人件費を削るために非正規雇用を拡大。「就職氷河期」に直面した若者は安定した職を得ることが困難となり、社会には閉塞感が漂いました。
労働者派遣法の改正で派遣労働が自由化されましたが、その裏でサービス残業やリストラが進み、働くことの不安が増していった時代でもあります。
🧭 日本の“働き方改革”──理想と現実のはざまで
「働き方改革」元年と期待
2000年代以降、非正規雇用が約3割に達し、「ワーキングプア」や「ブラック企業」といった言葉が登場します。こうした流れを受け、2016年、政府は「働き方改革実現会議」を立ち上げました。
2018年の働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制や「同一労働同一賃金」が法制化され、働く環境の改善が本格化したように見えました。
しかしその恩恵を実感できたのは、都市部のホワイトカラーを中心とした一部の層。地方や中小企業では制度の浸透が遅れ、意識の差も埋まらないまま今日に至ります。
🦠 テレワーク、リスキリング、そして新しい労働観へ
2020年、コロナ禍は日本の労働観に大きな転機をもたらします。テレワークや時差出勤が急拡大し、生活と仕事の境界線が曖昧になった一方で、孤独や労働時間の把握の難しさといった新たな課題も生まれました。
現在では、ハイブリッドワーク、副業容認、リスキリング(再教育)など、柔軟で自律的な働き方が求められるようになっています。
春闘では物価高に対応した賃上げが進む一方、非正規・若年層・地方の待遇格差は残り、真の“働き方改革”には道半ばといえます。
🌏 中国と日本──異なる道、交差する課題
中国と日本、歴史も制度も異なりますが、「生活の質を高めるための労働環境改善」という点では、いまや同じスタートラインに立ち始めたようにも見えます。
日本が数十年かけて乗り越えようとしている課題に、中国は今、直面し始めているのかもしれません。そして両国に共通しているのは──「働き方」は“制度”ではなく“文化”であり、“意識”の変革なしには本当の変化は訪れない、ということです。