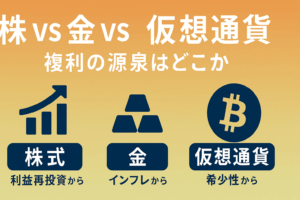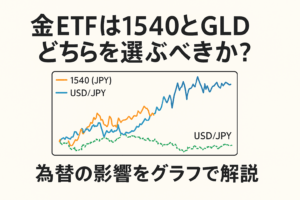2025年、トランプ大統領が再び打ち出した輸入品への関税政策が、思わぬところに火種を落とした。アルミニウムとアイルランド産濃縮液にかかる関税が、炭酸飲料業界の巨頭──コカ・コーラとペプシの競争構造を静かに揺さぶっている。
缶か、ボトルか。 この選択が、価格・環境・戦略の三方向で、企業の未来を分け始めている。
関税がもたらした目に見えない“重さ”
トランプ政権の関税政策には、2つのキーワードがある。
- アルミニウム関税(25%)
- アイルランド産濃縮液への10%関税
これらは、特にペプシコ社にとってダブルパンチとなった。
- ペプシはアイルランド・コーク州に主要な原液製造拠点を持ち、関税が直撃
- 米国内では缶製品比率が高く、1缶あたり0.02ドル程度のコスト増が発生
一方、コカ・コーラ社は濃縮液をジョージア州やプエルトリコで生産し、ペットボトル展開に重点を置いていたため、これらの関税による影響は軽微に抑えられている。
出典:
Beverage Digest
WSJ – The Trump tariffs are tilting the scales in the Coke vs. Pepsi battle
缶のコスト、ボトルのリスク──環境との両立は?
コストを抑える戦略として、コカ・コーラはペットボトル比率の増加を進めてきた。実際、CEOのジェイムズ・クインシーは2025年2月のインタビューで「アルミ缶が高価になれば、ペットボトルに注力する」と明言している。
しかし、それは別の批判を呼ぶ判断でもある。
- プラスチック容器使用の増加は、環境団体からの反発を招きやすい
- 同社が掲げていた「2030年までに再生素材比率を35〜40%へ引き上げる」という目標の進捗も遅れているとの指摘がある
環境対応とコスト圧力。企業が選んだ容器の背後には、こうした見えにくいトレードオフが潜んでいる。
出典:Coca-Cola Sustainability Update 2024
コーラの中身は同じでも、戦う土俵は違う
コカ・コーラとペプシは、同じ炭酸飲料市場を舞台にしながらまったく異なるゲームを展開している。
| コカ・コーラ | ペプシ |
|---|---|
| クラシックなブランド集中戦略(例:Coca-Cola, Sprite) | 限定フレーバー、カルチャー戦略(例:スポーツ・音楽) |
| 世界的に統一されたブランディング | ローカル色の強いキャンペーンや提携 |
この違いが、関税や環境対応といった「変化への耐性」にもつながっている。
ボトルか缶かだけじゃない──企業構造の違い
関税の影響を冷静に受け止めるには、企業全体の構造を比較する視点が欠かせない。
| 項目 | コカ・コーラ社 | ペプシコ社 |
| 売上高(2024) | 約471億ドル | 約918億ドル |
| 主力事業 | 炭酸・非炭酸飲料 | 炭酸飲料+スナック(Frito-Lay) |
| 炭酸飲料依存度 | 高い | 相対的に低い |
ペプシは飲料単体ではコカ・コーラに及ばないものの、Frito-Layやゲータレードなどの食品・スポーツ飲料事業が強く、関税影響を“分散吸収”できる体質を持っている。
シェアの地殻変動:二強の均衡に小さなひずみ
2023年の米国炭酸飲料市場(販売量ベース)のシェアは以下のとおり。
| 企業名 | 市場シェア(%) |
| コカ・コーラ | 19.2 |
| ドクターペッパー | 8.34 |
| ペプシコ | 8.31 |
| その他 | 64.15 |
ドクターペッパーがペプシをわずかに抜いたのは、低糖質製品のヒットなど一時的要因とみられるものの、二強体制の揺らぎを象徴する現象でもある。
結論:コーラは甘くても、競争は渋い
関税は、消費者の口に入る前の「裏側」を大きく揺さぶった。
- 缶かボトルか
- アメリカかアイルランドか
- 飲料一本か、多角展開か
その“静かな選択”の積み重ねが、今日の炭酸業界に“目に見えない格差”をもたらしている。
WSJが言うような「戦争」ではない。だがこれは明らかに、選択を迫られる時代の分岐点だ。