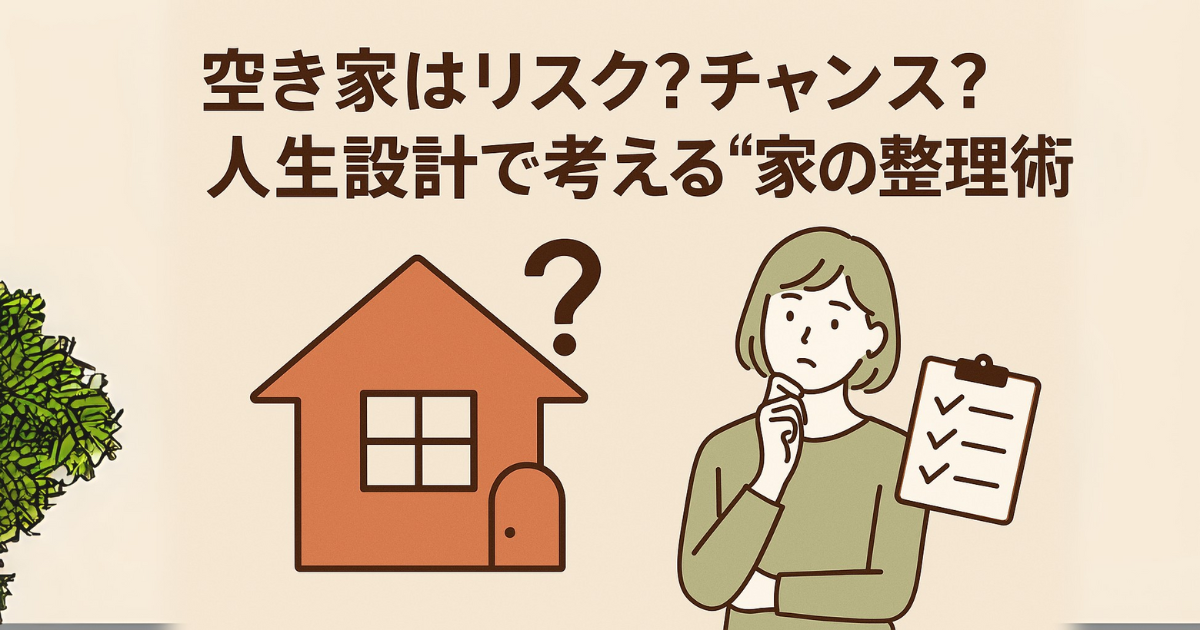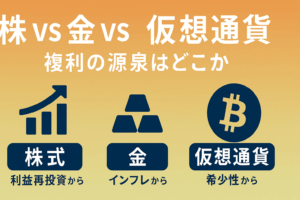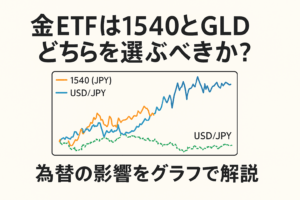空き家が急増しています。総務省の調査によれば、2023年には日本の空き家が**900万戸(空き家率13.8%)**に達し、過去最多を記録しました。ですが、空き家は単に「放置されて困るもの」ではありません。うまく活用すれば、生活の負担を減らしたり、新しい選択肢を生む資産にもなり得ます。
この記事では、空き家の現状と背景を整理したうえで、「空き家を放置すると何が起きるのか」「どう活かすことができるのか」を、生活者目線で分かりやすく解説します。
空き家の現状:過去最高を更新し続ける空き家率
まずは空き家の増加状況を、データから見てみましょう。

出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(FPTRENDY.COM編集)
今や7軒に1軒は誰も住んでいない家。空き家率は1988年の9.4%から35年で約1.5倍に上昇しており、右肩上がりの傾向が続いています。地方だけでなく都市部でも、空き家の増加は身近な問題になっています。
なぜ空き家が増えているの?
空き家が増えている背景には、いくつかの理由があります。
1. 人口減少と世帯数の変化
日本では人口そのものが減っており、高齢化も進んでいます。かつては増加していた世帯数も、今後は減少傾向に入り、家が余る構造的な要因になっています。
2. 家が余っている
新築住宅の供給が多く、世帯数以上に家が建てられてきた結果、「余る家」が生まれています。需要に対して供給が過剰な状態が続いています。
3. 壊すにもお金がかかる
解体費用は意外と高く(木造住宅でも100〜200万円程度)、さらに固定資産税も特例で安くなるため、放置されやすいのです。
4. 気持ちの整理がつかない
「親の家を壊したくない」「思い出があって手放せない」など、感情的なハードルも大きな要因です。
空き家を放置するとどうなる?
- 固定資産税や維持費がかかり続ける
- 台風や地震で倒壊すれば賠償責任の可能性も
- 景観や治安の悪化から、近隣トラブルに発展することも
法律の改正により、倒壊やごみの不法投棄など、周囲に悪影響を与える空き家は「特定空家(倒壊や衛生上問題のある空き家)」として認定され、固定資産税の優遇がなくなる場合があります。
空き家をどう活かせばいい?
空き家は、売るだけが答えではありません。暮らしに合わせて「維持・貸す・解体・相続対策」など、いくつかの選択肢があります。
● 売却や貸し出しで資産に
- 空き家バンク(自治体が管理するマッチングサービス)に登録し、移住希望者などに貸す・売る
- 一部の自治体では、リフォーム費用の補助制度もあります
● 相続を見据えて話し合う
- 「実家をどうするか」は親が元気なうちに家族で話すのが理想
- 兄弟で意見が合わずに放置されるケースも多いため、早めの対話が大切です
● 解体して土地活用も
- 建物を解体すれば、土地の売却や駐車場活用も可能に
- ただし解体費用や税制の変更点に注意が必要です
地域によって異なる活用法
都市部と地方では、空き家の活用方法やニーズに違いがあります。
- 地方:移住者向けの住宅ニーズが高く、空き家バンクで成約に至るケースも。DIYリフォーム付きで賃貸やシェアハウスにする事例もあります。
- 都市部:狭小地などを解体して駐車場にする、土地を整理して売却するなどの活用法が一般的です。
実際の活用事例
- Aさん(50代)は、実家を相続したものの住む予定がなく、空き家バンクを通じて移住希望の若者に貸し出し。家賃月5万円の副収入に。
- Bさん(60代)は、老朽化が進んだ空き家を思い切って解体し、月極駐車場として活用。毎月3万円の収益を確保。
このように、空き家は放置せずに動き出せば「収入源」にも「地域貢献」にもなります。
こんなときはFPに相談してみよう
「空き家をどうしたらよいかわからない」と感じたら、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみるのも一つの方法です。FPはお金の専門家ですが、家や相続、ライフプラン全体のバランスを見ながらアドバイスできます。
FPに相談するメリット
- 家計の負担や相続を踏まえたアドバイスがもらえる
- 税金や補助金制度の活用法を知ることができる
- 家族との話し合いを整理するサポート役になる
相談のポイント
- 空き家の所在地、築年数、名義などの情報を用意しておくとスムーズです
- 不動産の仲介が必要な場合は、FPから宅建業者の紹介を受けることもできます
まとめ:空き家を“将来の自分の選択肢”に変える
空き家は「不要なもの」ではなく、「整理すれば役立つもの」になる可能性があります。放置するのではなく、どう活かすかを家族で考えることが、結果的に自分たちの人生設計を豊かにします。
不安な時は、FPなどの専門家を味方にしながら、早めの一歩を踏み出してみてください。