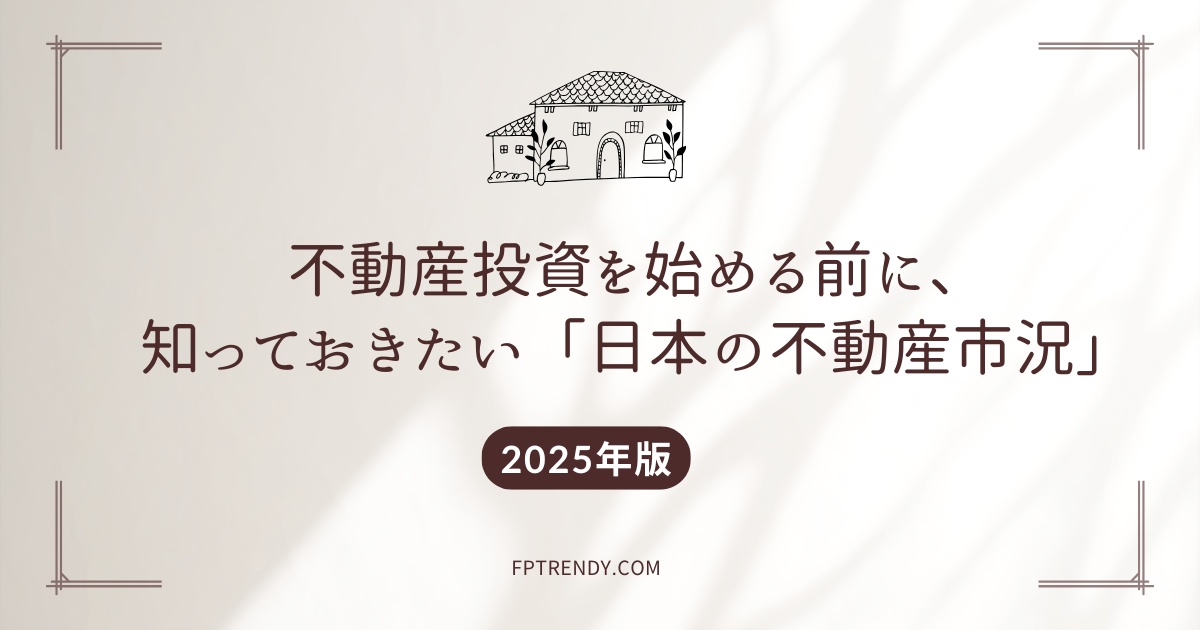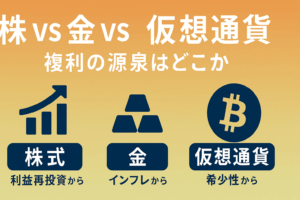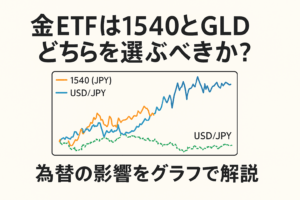かつては「節税対策」としても注目されていた不動産投資。
特に都心の高級タワーマンションを相続前に購入し、評価額を大きく下げて相続税を抑える——いわゆる**「タワマン節税」**は、富裕層を中心にひそかなブームとなっていました。
しかし、この「行きすぎた節税」を是正すべく、2024年から区分マンションの相続税評価方法が大きく改正されました。
この章では、その改正内容と、私たちの不動産投資にどのような影響があるのかを丁寧に解説します。
なぜ変わった?タワマン節税の問題点
これまでの制度では、タワーマンションなどの区分所有物件は、相続税評価額が「実勢価格(売買価格)」よりも大幅に低く見積もられる傾向がありました。
たとえば、3億円で購入したタワマンの評価額が1億円以下になるケースも珍しくありませんでした。
これは、評価が「固定資産税評価額」や「路線価」で算出されるためで、実際の価格とはズレが生じていたのです。
この仕組みを利用し、相続直前にタワマンを購入して評価額を下げ、大幅な節税を図るという手法が横行。これが「タワマン節税」と呼ばれるものでした。
2024年、評価方法がどう変わったのか?
新制度では、このズレを解消するため、区分マンションの相続税評価額が、実勢価格により近づくように見直されました。
具体的には、「評価乖離率」という新しい指標が導入され、築年数・所在階・敷地の持分割合などの条件をもとに、評価額が補正される仕組みとなりました。
結果として、多くの区分マンションは、従来よりも相続税評価額が大幅に上昇します。とくに影響が大きいのは、以下のような物件です:
- 築浅である(築年数が浅いほど補正率が高い)
- 高層階に位置する(上階ほど評価アップ)
- 敷地持分が少ない(=建物面積に比べて土地の価値が低い)
実際の影響はどれくらい?
ある都心のタワーマンション(売買価格:3億4,000万円)の例では、評価額が旧制度で約1億円→新制度では1億8,000万円超にまで引き上げられています。
実勢価格の3割評価だったものが、5割以上になるというインパクトです。
とはいえ、まだ戸建てと完全に同じ評価(=実勢価格の6割程度)には達していません。
それでも、「節税効果は明らかに減った」と言ってよいでしょう。
それでも区分マンションは“使える”のか?
改正によって節税メリットは薄れたとはいえ、区分マンションの魅力が完全に失われたわけではありません。
特に都心の好立地物件や、ファミリー向け区分マンションは、以下の理由で依然として人気があります。
- 比較的流動性が高いため、いざというときに売却しやすい
- 銀行の融資を活用しやすく、少額の自己資金で始められる
- 安定した賃料収入を得やすい
- 投資用だけでなく、自宅用途としても売却可能
つまり、「節税目的ではなく、資産運用や資産分散の一環」としては、引き続き有力な選択肢なのです。
一棟投資や賃貸物件にも影響はある?
なお、今回の改正は区分所有マンションに限定されたものであり、一棟アパートや戸建賃貸などには直接の影響はありません。
これらは従来通り、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価され、さらに賃貸中であれば**貸家・貸家建付地の評価減(最大30%程度)**も適用可能です。
つまり、相続対策として一棟物件のニーズが今後高まる可能性もあるでしょう。
まとめ:節税から運用重視へ。今後の不動産投資のスタンス
相続税評価の見直しにより、「節税目的だけで不動産を買う」時代は終わりつつあります。
とはいえ、不動産は依然として現物資産としての価値が高く、インフレに強く、かつ安定した賃料収入を得られる投資先です。
大切なのは、「節税」だけでなく、運用益や資産形成、将来的な活用を見据えて投資を考えること。
その視点を持つことで、不動産は今後も有効な選択肢であり続けるはずです。
次回(第4章)では、そんな現物不動産の投資に潜む「思わぬ落とし穴」について深掘りしていきます。実際にありがちな失敗例や見落としがちなポイントを見ていきましょう。
📚 不動産投資シリーズ一覧