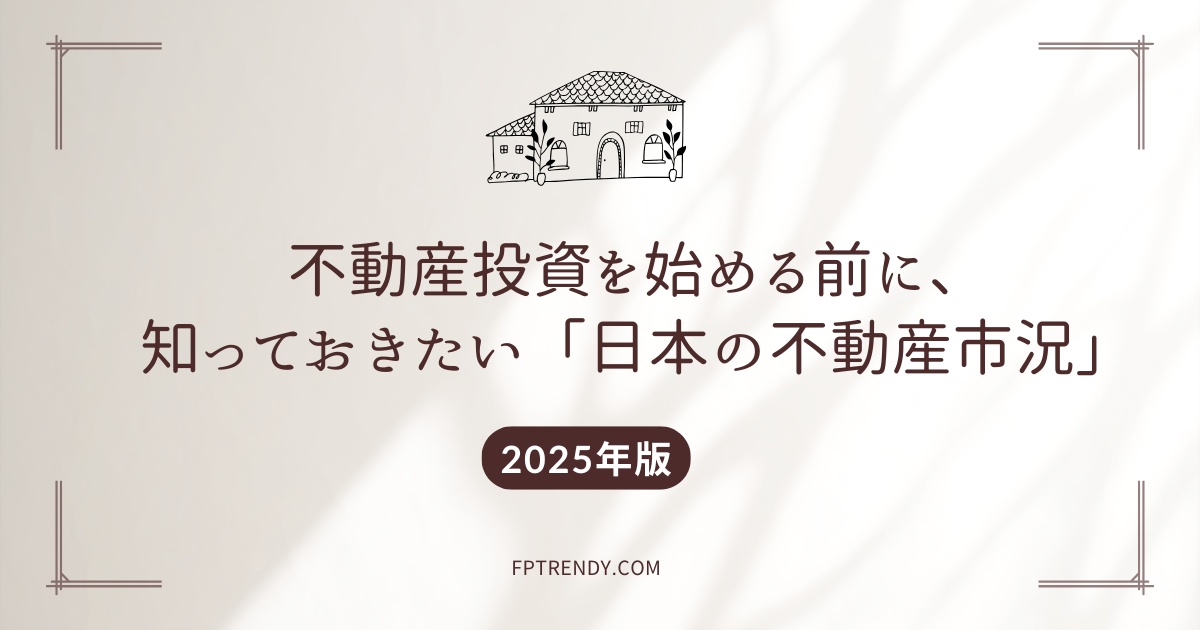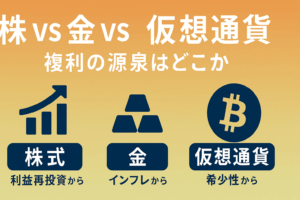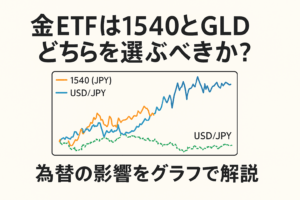不動産投資と聞くと、「とりあえずマンションの一室を買えばいいのでは?」と思う方も多いかもしれません。
しかし実際には、マンション、アパート、オフィスビル、さらには土地(底地)やJ-REITといった金融商品まで、さまざまな投資対象が存在します。
それぞれの物件タイプには、「収益の上がり方」や「手間のかかり方」、「売りやすさ」などで大きな違いがあります。
この章では、それぞれの特徴をわかりやすく整理しながら、どのような人に向いているのかを探っていきます。
区分マンション、一棟ビル、土地——どれを選ぶ?
まずは「現物不動産」として代表的な3タイプを見ていきましょう。
たとえば、マンションの1室などを所有する「区分所有」は、比較的少額で始められ、管理の手間も少ないのが特徴です。修繕や共用部の管理は管理組合が行うため、不動産の知識が少なくてもチャレンジしやすいでしょう。ただし、入居者が一人退去すると収入はゼロになってしまうため、空室リスクには注意が必要です。
一方、「一棟所有」は、アパートやビルをまるごと自分で持つスタイル。複数のテナントから家賃収入を得られるので、安定した収益を狙いやすくなります。自分の判断で建物の修繕やリニューアルも進められるという自由度の高さも魅力です。ただし、初期投資が大きく、物件管理やトラブル対応の負担も重くなります。
そして、あまり知られていないのが「底地」と呼ばれる土地の投資です。借地権付きの土地を所有し、長期にわたって地代収入を得るスタイルで、家賃のようなクレームも発生しにくく、比較的安定した収益を見込めます。とはいえ、利回りは低く、自己使用もできないなど、用途が限られる点に注意が必要です。
住居系 vs 事業系、それぞれの投資スタイル
次に、「どの用途の物件に投資するか」という観点で見てみましょう。
最も一般的なのは「住居系」の不動産です。アパートやマンションなど、人が住むことを前提とした物件は、景気の影響を受けにくく、長期的に安定した賃料収入が期待できます。空室リスクへの対応もしやすく、設備の修繕などもある程度見通しを立てやすいのが利点です。ただし、築年数が進むと賃料が下がりやすいという点には注意が必要です。
一方、「事業系」の不動産は、オフィスや店舗、ホテルなどが中心です。こちらは住居系よりも賃料単価が高く、うまく運営できれば高い収益が狙えます。また、テナントが内装工事や原状回復費用を負担するため、オーナーのコストは比較的抑えられます。ただし、景気の変動に左右されやすく、テナントが退去した場合の空室期間が長引く可能性もあります。
少額から始められる投資もある
「いきなり物件を買うのは不安…」という方には、少額で始められる不動産投資商品もあります。
たとえば、「小口化商品」は、実物不動産を多数の投資家でシェアして所有するタイプで、100万円前後から始められるのが特徴です。特に任意組合型の商品では、相続税評価を「現物不動産」として扱えることから、資産承継対策としても注目されています。ただし、流動性が低く、償還期間(解約できる時期)が決まっている点には注意が必要です。
また、証券市場で売買できる「J-REIT(不動産投資信託)」も人気の選択肢です。プロが運用し、少額から投資できるうえ、売却も株式のように自由にできます。ただし、こちらは相続税評価が時価となるため、相続目的にはやや不利になる場合もあります。
投資目的に応じた選択がカギ
不動産投資には「正解」があるわけではありません。重要なのは、「何のために投資するのか?」という目的を明確にすることです。
たとえば、初心者の方や初めての投資には、管理の手間が少なく始めやすい区分マンションやJ-REITが向いているかもしれません。安定収益を狙って長期で保有するのであれば、一棟アパートや底地のようなスタイルが合うでしょう。相続対策を視野に入れている方には、小口化商品や現物の不動産が有効です。
まとめ:タイプを知れば、不動産投資はもっと自由になる
不動産投資は、「物件を選ぶこと」=「リスクとリターンを選ぶこと」に直結します。
一見すると難しそうに見える不動産の種類ですが、それぞれの特徴と自分の目的さえしっかり理解していれば、無理なく、そして効果的に運用することが可能です。
次回(第3章)では、2024年に見直された「相続税評価の改正」と、それが不動産投資にどう影響するかについて解説していきます。相続対策としての不動産活用を検討している方は、ぜひご覧ください。
📚 不動産投資シリーズ一覧